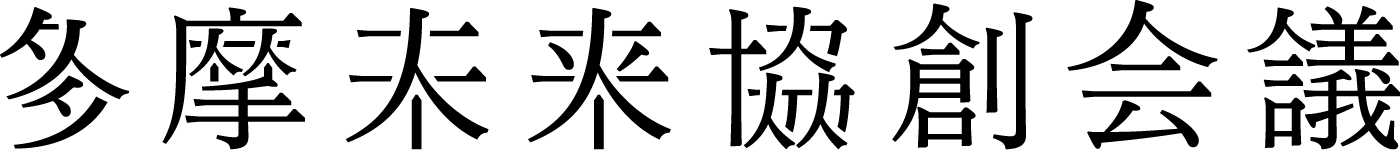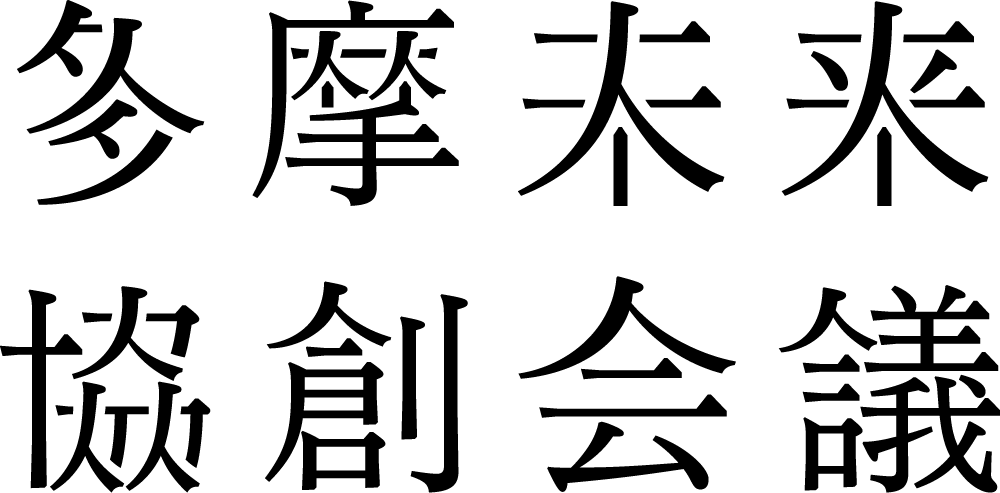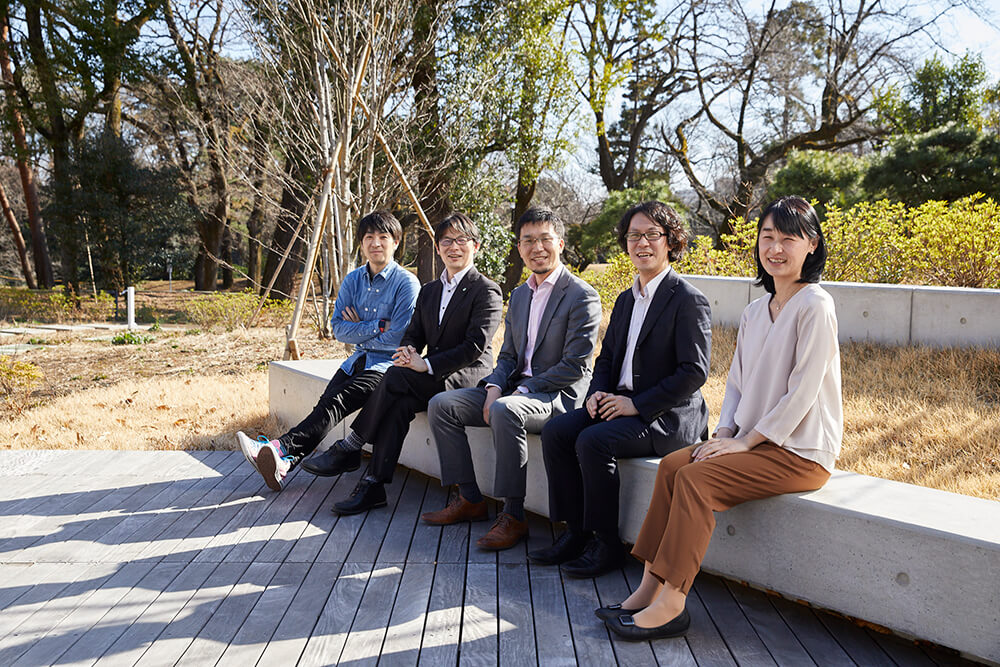もっと地域に住民が関われる余地をつくるには? ― 人の行動を変容させるシカケと持続可能な公共の関係 ―
プログラムオーナーが「Dialog」「Monolog」を通して立てた問いに対しての“解”を探るミートアップ。地域で活動している4名の参加者が、自身のバックグラウンドと課題を順番に話し、意見を出し合います。メンバーたちの活動領域は実にさまざま。全員参加の活発な議論が繰り広げられました。

- 海野千尋(ArrowArrow 代表理事)
- 中村由佳(国分寺地域包括支援センターもとまち 高齢者見守りコーディネーター)
- 北池智一郎(タウンキッチン 代表取締役)
- 早坂 顕(汎 代表取締役)
- 伴 真秀(社会イノベーション協創統括本部 企画室)
- 森木俊臣(社会イノベーション協創統括本部 東京社会イノベーション協創センタ)
- 白澤貴司(社会イノベーション協創統括本部 東京社会イノベーション協創センタ)
- 有本英生(中央研究所 企画室)
- 酒井博基(多摩未来協創会議ディレクター/D-LAND 代表)
「地域で働く」の選択肢を増やす
海野千尋さんが代表理事を務めているArrowArrowは、「子育てや介護等の理由に左右されず、選択肢あふれる社会の創造」をビジョンに掲げて活動しているNPO法人です。

取り組みのひとつである「ママインターン」は、子育てなどで仕事を離れたけれど、社会復帰したいと考えている女性と地域の企業をつなぐ事業です。週に数日、2〜3時間のインターンを通して働くことのイメージをつかみ、再就職への第一歩を後押し。そのままインターン先の企業に就職するケースも多くあります。
ママインターンで体験できる業務は、店舗スタッフや営業、ウェブ管理など多岐にわたります。「ママインターンを受け入れたいと考えている企業に対しては、ヒアリングの段階で、短い時間でできる仕事を切り出せるかを必ず聞いている」と海野さん。「フルタイムでやってもらうような仕事だとまずできないので、『全体の作業のなかのこの部分だけをやる、という形にできますか?』と聞くことが多いですね」と続けます。
多摩未来協創会議ディレクターの酒井から、同じように業務を切り出して委託するクラウドソーシングとの違いについて聞かれた海野さんは、「クラウドソーシングは、そもそも企業側に委託業務を管理するマネジメントスキルがないと発注できない」と話します。

「そういった意味で、ママインターンは、企業側の要望を踏まえて働く側にヒアリングし、チューニングしたうえで業務をつくり出すという作業があります。それから、顔の見える関係性である点も重要で。企業側と働く側が近くに住んでいるので、たとえば企業側が店舗で売り出したいものがあったとき、働く側は地域特性を知っているので『こういうふうに売り出したらいいと思います』と提案できる。そういった、同じ地域だからこそ話が通じることは大いにあります。
一方、働く女性の立場で言うと、企業側と顔の見える関係性ができていればいるほど、なにかあったときにすぐ相談ができます。子どもが熱を出したとき、『残りの仕事は明日の夕方までになんとかするので、今日だけ帰らせてもらえますか』と言えたりするんです」
ここで、日立製作所の伴さんから意見があがりました。
「そういう、企業と働く人の間で行なわれている“チューニング”って、記録として残っていたりするんですか? というのもママインターンは、いい意味で、ウエットで曖昧な交渉ができていますよね。だからこそ、たとえば『○○さんは今日、早く帰っちゃったけど、そのぶん余分に頑張ってくれた』っていう情報を、なにかしらの形で残すことができるとさらにいいんじゃないかと思いました。単に仕事ができる・できないで測るのではなくて、『この人は地域のなかですごくいいパフォーマンスを発揮する』といった地域への貢献度が見えると、その人の地域とのつながりや、地域で活動していることの意味性が深まるのではないでしょうか」

伴さんの話に対して、海野さんはママインターンで行っているワークショップについて話します。
「企業とマッチングする前に、インターンの参加希望者に3回ぐらいワークショップをするんですが、実は私たちが一番注力するのはそこなんです。子どもを持ちながら働くなかでは、どうしても自分のコントロール配下におけない状況になることがあります。このワークショップは、そのとき、企業側に対してどういう貢献の仕方ができるかをシミュレーションしてもらうものです。子どもが熱を出したときにどういうリスクヘッジができますか?っていうのも聞きますし、どんなふうに勤め先に伝えるかをロールプレイングしてもらう。すると、なにかあったときに、イメージトレーニングしたからできますよ!と背中を押せるんです。困ったとき、企業側に『こう変えるのでこうしませんか』と提案できたら、お互いが歩み寄って交渉できると思います」
「ママインターンの仕組みを通して、お金を稼ぐ手段の幅が広がるっていうことだけじゃなく、地域のなかでの社会関係資本みたいなものが、企業側にも、個人のなかにもたまっていくようになると面白いですね」と伴さん。
海野さんは、「そこまでいけたら、もう嬉しさしかありません」と語りました。
高齢者との新しいつながり方
高齢者見守りコーディネーターとして、市民とコミュニケーションをとり、フレイル(加齢によって心身が衰えること)予防の取り組みを推進したり、介護にまつわる相談窓口などの役割を担っている中村由佳さん。2020年度から始まったばかりの事業であるため、地域の企業や、地域で活動している方とつながるヒントが得られたらと、今回のミートアップに参加したそうです。

中村さんの業務内容を聞き、日立製作所の白澤さんから「コミュニケーションをとるうえでは、たとえば寝たきりの人とデジタルデバイスを使える人で方法が異なると思うのですが、どんな方が多いのですか?」と質問があがりました。

中村さんは「歩いて出かけられるけれど、身体が少し虚弱になっている方など、フレイル予防の効果が期待できる方を想定しています」と言い、こう続けます。
「デジタルデバイスを使いこなせるような方や、高級住宅街に住んでいる方たちは、自分たちで情報を得て解決しているので、あまり接する機会がありません。どちらかというと、情報へのアクセスが難しい人。ご家族から相談を受けることもありますが、孤立してしまっている方だと、近所の人から『心配な人がいるんだけど』とご連絡をいただくケースもあります。そうして当事者とつながり、環境を作ってはじめて情報を渡せるようになるんです」
「近所の集まりなんかに出てこられる人はまだいいですよね。問題は、出てこられない人に対してどうアプローチするか」と日立製作所の森木さん。公民館などでは、定年退職を迎えた人に向けて、地域デビューのきっかけとなるような講座が開かれています。そういった講座に参加するモチベーションがある人や、もともと自治体の活動に参加している人は、自分から地域に出ていくケースが多いのです。

中村さんは「一番地域の人と集ってほしいのは、退職までずっと仕事に集中していた男性で、地域とのつながりのない方。そういう方に対しては、“足でかせぐ”ではないですが、会いに行って信頼関係をつくることが必要です」と語ります。
伴さんからは「ひょっとしたら、今40、50代の人に対して手を打つことも大事なのかもしれませんね。たとえば、地域のコミュニティに早くから参画する仕組みとか。仕事だけじゃなくて、地域にも貢献できる人間なんだっていうマインドセットができたらいい」という意見が出ました。
タウンキッチンの北池さんは「公民館に行かないお年寄りも、商店街の整形外科や鍼灸院には集まる」と話します。
「安い金額でマッサージしてもらえて、おしゃべりもできてっていう、オアシスみたいな場所になっているんでしょうね。公的機関に『地域デビューしませんか』と言われても面倒なので、民間のサービスに置き換えているんだろうと思います。
一方で、公共の役割はそういった民間サービスの網の目からこぼれてしまった人たちをいかにすくっていくかどうかですよね」
高齢者とのコミュニケーションは、顔を合わせて話すことが基本になっている現状があります。それに対して「ITでつなげられるといいですよね。会わずとも、どこかでつながりを感じることが大切」と日立研究所の有本さん。ただし、高齢者のITに対する拒否感をどう払拭するかは課題です。

汎の早坂さんは「高齢者の方たちが、数十年間をかけて築いてきた“つながる”感覚を、バーチャルで代替するのは難しい」と指摘。コロナ禍においても、ステイホームに徹するのではなく「なんらかの方法で、対面しても感染の危険はないよと安心させてあげることができなきゃいけないと思います」と続けました。
小さな民意を吸い上げ、街づくりに活かす
多摩エリアを中心に、創業支援を通じたまちづくりに取り組んでいる北池智一郎さん。活動のベースになっているのは、“市民の細やかなニーズに応えられるのは市民自身である”という仮説です。
街には、違法駐車や空き家問題、ゴミの投棄など、小さな困りごとが点在しています。それらは住民にとって切実な問題である一方、行政や企業が事業として解決にあたるのは難しいのが現状。「ならば自分たちの力でなんとかしよう」という人に対して、創業支援という形で支えているのです。

今回のミートアップについて、北池さんは、日立製作所が「デバイスなどを通して市民からデータを吸い上げ、分析・加工して必要な人に届ける」ことを目指している点を挙げ、「そこが、日立さんと僕がご一緒できる結合点かなと思います」と語りました。
さらに、「街での暮らしは、結局、公共サービスに支えられている」と続けます。
「市民がそこに関与していく術は、選挙で議員を選ぶことや、市役所などに対して声を上げることだと思いますが、実際は、サイレントマジョリティの声を政策に反映させることは難しいのが実情だと感じています。空き家問題であれゴミの投棄であれ、問題に一番気づいているのは、近隣に住んでいる一人ひとりの住民なんですよね。だからこそ、データを市民の大きなメッセージとして行政に届けるといった活かし方ができたらいいなと考えました」

ここで伴さんが、北池さんが取り組んでいる空き家問題と“データ”の関係について話します。
「ひとつは治安の問題がありますよね。空き家の軒数など、治安に応じて街の見た目も変わってくる。街のどのあたりの治安が悪いのかっていうのは、空き家の数や分布、人の流れといった観点からデータを見て考えていくことができると思います。つまり、パブリックセーフティ(AIやビッグデータを利用して犯罪や事故などを防止すること)の話です。それから、空き家の利活用についてもデータを活かす余地がありそうです」

次に北池さんが身近な問題として挙げたのは、道路での停車について。毎日使う道の自転車レーンにいつも複数のトラックが停まっていて、そこを自転車で通るときにトラックを避けて車道に出なければならないそうです。通報するほどではないけれど、きっとみんなが不満を抱いている“街での困りごと”。これに対して伴さんは、「小さな民意をどうやって地域に反映させるかって、すごく大きな課題ですよね」と返します。
「民意を吸い上げて街づくりに落とし込むことを、どうやったらテクノロジーでできるかなと考えたことがあります。自分で問題に気づく人もいれば、人に言われて『そういえばここ不便だよね』と思う人もいる。前者はもともと想いがあるからいいんですけど、大きな民意にするときには、後者が重要なのではないでしょうか。たとえば交通量やトラックの違法駐車を定点観測して、そこから“みんなが気づいているわけではないけれど、実は改善したほうがいい小さなこと”を見える化するようなことができればいいなと思います」
再び集うためのテクノロジーと“優しさ”
多摩エリアに住む早坂さんは、“アートとテクノロジーをつなぐ”をコンセプトとした企業「汎」の代表でありエンジニア。日本科学未来館内のARを使ったデジタルコンテンツや、東京駅の中を流れる風をLEDでビジュアライズするプロジェクトなど、幅広い領域で活動しています。
もともと社会学を専攻していたこともあり、「もうちょっと具体的に、世の中でギブアンドテイクができる仕事がしたい」と考え、ミートアップに参加しました。

早坂さんはステイホームの期間、エンジニアの視点からアフターコロナの世の中のあり方について考えていたといいます。
「これからは、リモートツールを使い、フィジカルディスタンスを空けるという“タイトでクリーン”な世の中になっていくと思いますが、僕はそっちに振りすぎることに危機感を持っています。というのも、僕はずっと仕事でテックと表現を扱ってきたのですが、テックを使った表現をしようとすると、どうしてもタイトでクリーンになりがちなんです。でも人間って、本当はウエットでメッシーですよね。その断絶をずっと感じ続けてきました。テックを使って社会をつなげようとするときには、それを乗り越えなきゃいけない。コロナで世の中が変わってきたなかでは、タイトでクリーンじゃなく、ボブマーリィ的な優しさがより必要になってくると思うんです」

テクノロジーと“優しさ”で人々がつながる。早坂さんは地域のお祭りを例に挙げ、さらに語ります。
「たぶん今年は、お祭りは中止になりますよね。でも本当は、安心できる環境をつくって、そのうえでみんなで集まることができるよと言えるようにしたい。もうこれ以上、コミュニケーションと無縁になっている今の状態を、社会的動物である人間が受け入れられるとは思えないので、僕はそれをなんとか解決していく仕事をしなきゃいけないと思っています。
それから、今回一番憤ったのが、経済的にも身体的にも余裕がある人はステイホームを謳歌できていますが、そうじゃない人のほうが多いんですよね。弱者は、こういうときにやっぱり取り残されてしまう」
偶然にも伴さんは最近、森木さんとの雑談のなかでお祭りについて話したといいます。
「このままお祭りが消滅しちゃったら寂しいよねと話していて、じゃあどうしたら継続できるかと考えました。『この集団は安全だ』ということをすぐに判断するのが難しいとすると、お祭りは密集してこそ楽しいものですが、せめて輪番で開催できないかと。1年に1回大きなお祭りをやるんじゃなくて、1月は1丁目の人、2月は2丁目の人、みたいに小さなお祭りを開くんです。それでコロナに感染しないという保証はまったくないのですが、不特定多数の人がわあっと集まるのではなく、特定の地域コミュニティの範囲で。ある程度素性の知れた人同士だと、『こういうことに気をつけようね』とか、共通のルールがつくりやすくなるんじゃないかと思います。人が集うことを段階的に回復していくには、人の気持ちや信頼関係、つながりをうまく使うやり方が有効かもしれません」

こうして、約2時間にわたるミートアップは終了しました。
今後は交わされた意見やアイデアをもとに、コラボレーションの可能性を日立製作所と参加者が引き続き検証。個別にコミュニケーションをとり、議論を深めながら、協創プロジェクトの社会実装や事業化を目指していきます。
これまでは、大きな企業が地域の人と話そうとするとき、「企業=ホスト/住民=ゲスト」、あるいは「企業=発注側/地域で活動する人=受注側」という関係になってしまうケースが多くありました。
多摩未来協創会議がミートアップを通じて目指しているのは、両者がフラットな関係性で対話し、新しい「地域×企業」の協創のきっかけをつくること。
今回のミートアップは、その第一歩となりました。
ミートアップ終了後の会場では交流会が開かれ、自由なディスカッションが続いていきました。
ここから、多摩地域の未来を共につくる、新たなつながりが生まれていくはずです。