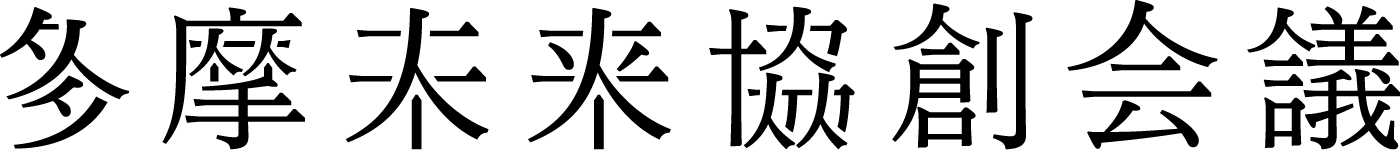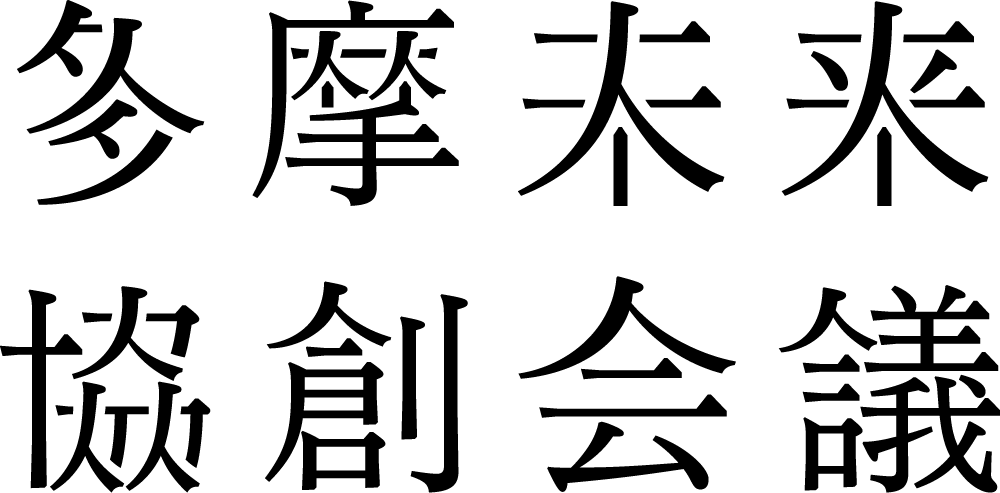ウェルビーイングへとつながる新しい知を生み出す、生活者主導のリビングラボをつくるには?
プログラムオーナーが「Dialog」「Monolog」を通して立てた問いに対しての“解”を探るミートアップ。3名の参加者が、日野市が模索する持続可能な生活者主導のリビングラボについてのアイデアを発表しました。それぞれの異なる視点で提案されるこれからのリビングラボのあり方は、その概念を捉え直し新しい地域社会へと思考を向かわせてくれるものでした。

- 大庭将広(日野市民/企画制作・広告代理業)
- 須崎貴寛(日野市議会議員)
- 小泉満(東京都立産業技術大学院大学講師/オープンポスト合同会社代表)
- 中平健二朗(企画部 企画経営課)
- 鈴木賢史(企画部 企画経営課)
- 酒井博基(多摩未来協創会議ディレクター/D-LAND 代表)
「楽しそう」が入り口。伝わりやすいシンプルなテーマを設定するリビングラボ
最初の発言者となった大庭将広さんは日野市程久保地域のご出身。地元地域の自治会長を経験したりスタンプラリーを企画したりと、まちづくりに積極的に取り組んでいます。大庭さんはまずウェルビーイングについて、「人が幸福として考えやすいことはおいしいものを食べること」と位置づけ話しはじめました。

「リビングラボという場を前提に考えると、自分たちでつくったものをみんなで一緒に食べるということかと思います。日野市にはそれができる土壌があります」と大庭さんはいいます。
大庭さんの暮らす程久保は、里山の残る丘陵地です。多摩川の支流である程久保川沿いには水辺の生物が生息し、タヌキやハクビシンなども目撃されています。そこで農業を中心に据えたリビングラボのあり方を、大庭さんは提案しました。
「農業をやるには農業の知識だけではなく、生き物に関することや建築に関することなど、さまざまな知識や技術が必要になってきます。食育を軸にそういうものも学び受け継いでいくことで、地域の文化や伝統工芸の継承にもつながることが期待できます。またリビングラボにはいろんな人が集まるので、諍いが起きることもあると思いますが、それらもラボの一貫であり実験のひとつとして捉えることができると思います」
誰もがイメージしやすい「食」を軸に据えるという提案は、今回のミートアップに先立ち日野市の中平健二朗さん、鈴木賢史さんと、ファシリテーターを務める酒井博基の議論で出た「楽しいところから入り、様々な立場や視点から地域のいいところを伸ばしていく」というビジョンにも通じるものがあります。中平さんは過去に実施した、食をテーマにした場づくりの事例を共有しながら次のようにフィードバックしました。

「食べることは誰にとっても“自分ごと”なんですよね。たとえば最終的な目的として健康やヘルスケアリテラシーというものがあったとして、それを正面から教えられてもつまらない。ところがみんなで集まって一緒にお味噌汁を食べながら塩分の話をしたりすると、すごく興味を持って学んでくれるんです。リビングラボも同じように、研究者・被験者という境界がなく対等な立場で参加できる共通の学びの場であると思います」
またどんなテーマであっても、課題を自分のものとして捉えるところがリビングラボのスタートラインになると中平さんはいいます。どこかの誰かの課題ではなく、自分がそれについてどう感じるか、どこに思いがあるのかという当事者性を引き出すためのテーマ設定の重要性が、中平さんのお話から伝わってきます。
続いて、大庭さんの提案から新たな気付きを得た鈴木さんからもフィードバックがありました。

「これまでのリビングラボは、課題があってそれを解決したい人に呼びかけていました。課題を解決したい人はやはりパワフルな人が多いのですが、楽しさを軸にしていくとそこがガラッと変わりそうですね。また農業の場としては、畑に限らず公園や商業施設の空きスペースなど、市内で使える様々な場所が考えられるかと思います」
課題解決ということをリビングラボを開催するうえでどう位置づけるか、どこに開催の意義を見出すか。これがリビングラボのあり方を考えるひとつのポイントとなってきそうです。それについて中平さんが、リビングラボのベースの考え方を場に共有しました。
「課題に寄り添うというのがリビングラボの本質です。寄り添うことで疑似当事者性が生まれます。たとえば病気という課題があったときにその本人や家族の気持ちになると、テーマとするのは病気そのものだけではなく、それを取り巻く家族や病気とともにある日常生活とか、いろんなものが出てくると思います。その課題の全体感を見ることができるのが当事者性であり、現場視点での探究ができるというところがリビングラボのいちばんの意義だと思っています」
誰でも開催できる若者主体のリビングラボ
2人目の提案者はZoomでの参加となった須崎貴寛さん。2月に行われた日野市議会議員選挙で初当選した須崎さんは、現在26歳。多摩エリア全体を視野に入れたリビングラボや、そのなかでの日野市の位置づけを、若者視点で考えた発表となりました。

多摩エリアには大学が集積しているにも関わらず、就職を機に多くの人材が流出してしまうという課題に対し、リビングラボをプラットフォームとした環境整備を考えているという須崎さん。環境や持続可能性をテーマに世界の500都市以上で開催されているイベント「green drinks ※1」を参考に、一定のルールのもとに誰でも開催できるリビングラボを提案しました。
「ある程度のルールを設けたうえでビジョンを共有し、多摩エリアのいろんなところでリビングラボが開催されるようになるのが理想の状態です。オンラインを活用し学生などの若者が中心となって開催することで持続可能性が担保できるのではないかと考えました。また日野市にはPlanT(プラント)という創業支援施設があります。そこを30市町村のオンラインの拠点として、多摩エリア内の主催者が一堂に会するリビングラボのモデレーターのような役割を日野市ができると考えています」
同一のフォーマットだからこそ個性が見えてくるのではないかという須崎さんの提案に、鈴木さんがフィードバックします。

「それぞれの自治体の課題やテーマに寄り添ったリビングラボをいかに推進していくかという方向に自分の考えが固まりすぎていましたが、それに限らず『やりたい』と声を上げやすいというのは、実はリビングラボに必要なひとつの要素なのかもしれないと思いました。一気にハードルが下がるというか、その世界観が重要なんだなと」
中平さんも「誰でもリビングラボを開けるようになるというのは理想」といい、こう続けました。
「リビングラボの場の設定として、共有空間とか協創空間を表す『コモンズ』という表現がありますが、生活者視点で考えるとさまざまな場所がコモンズになり得ると思っています。たとえば、学校の課題を解決するとしたら学校で話すのがいちばん分かりやすい。実際にその場に立ってみると、理論だけで話すよりもよっぽど現場の知見が得られるんです。そういう側面からも、あらゆる場所でリビングラボが開かれるようになっていったらいいですね」

30の市町村があり420万人以上もの人が暮らす多摩エリアのあちこちで、多種多様なリビングラボが開かれる。そんな「どこでもリビングラボ」の可能性が、須崎さんの提案から見えてきました。「どうしたら若い人たちが参加したくなるのか」という酒井の問いかけに、須崎さんは「人からの紹介とメリットの打ち出し方」というふたつのポイントを挙げました。やはりいちばんは知り合いの口コミですが、2点目のメリットについて須崎さんは次のようなアイデアを出しました。
「リビングラボは企業も一緒にやっていくものなので、たとえば学生は長期インターンのようにして企業の業務にもアイデアを出す機会を設けたり、最終的には部分的に採用スキームをつくるというのも一案かと思います」
企業が提供できるものを一般の参加者に分かるように見える化するというアイデアは、学生だけでなく一般の参加者の関心や好奇心にもつながっていきそうです。
既存の枠組みとコラボするリビングラボ
最後の発表者は、東京都立産業技術大学院大学の講師としてシニア対象の履修証明プログラムを提供している小泉満さん。小泉さんは地域課題解決を軸としたアクティブラーニングプログラムとリビングラボの親和性について語りました。

「八丈島や檜原村という課題先進地域で学生たちが初期調査から課題の設定をし、その課題を解決するような事業を設計していますが、それが現時点では疑似起業体験に留まってしまっているという課題があります。履修生はすでに社会に出ている方ばかりなので、在学中はとても積極的に活動し優秀な事業計画を立てるのですが、修了とともに元の鞘に収まってしまう人が多い。これはすごくもったいないと思っています」
すでに社会を経験しているからこそ起業に対して慎重になってしまう履修生とリビングラボを結びつけ、産官連携のなかでつながりやサポートを得ながら課題解決に取り組むことで、新たな道を踏み出すことができるのでは、という小泉さんのアイデアに、中平さんがフィードバックします。
「リビングラボには、市民と企業など異質性のあるもの同士が出会い相互に作用する“新結合の場”としての役割がありますが、それは別の言い方をすると“越境の場”でもあると思うんです。リビングラボでは現場の視点を持ってそこからいろんなことを想起していくというのが非常に重要ですし、自身のテリトリーを抜け出して外部と接点を持つと、会社の中だけにいるのとは比べものにならないくらいのインプットがあります。自分の領域の外に出る越境というのもひとつの要素だと思いました」

続けて中平さんは、リビングラボに必要と思われるもうひとつの要素について、「関係性をデザインするデザイナー」の存在を挙げました。
「日野市は『ポストベッドタウン』というテーマを掲げて地方創生に取り組んでいます。日本は高度経済成長期から分離して特化して部分最適化をするということをずっとやってきて、その最たるものがこのベッドタウンです。それが成熟化を経て今は持続可能な社会をどうやってつくっていくかという段階にきて、社会のあり方を再構築しないといけない。それをどういう形で構成すべきかというところに、デザインの要素が必要です。リビングラボはそのデザインをみんなで学んでいく場だと思うんです」
誰かが正解を知っているわけではない持続可能な社会のあり方を、みんなで引き出して共有知としていく場がリビングラボであるという中平さん。その仕組みやプロセスの方法論を見つけるのが目下の課題であるといいます。
「一橋大学の野中郁次郎教授のSECI(セキ)モデル ※2 のように、知の循環や共有プロセスの方法論がある程度様式化されているものを地域にインストールできないかと考えています。それによって潜在的な課題を表出して共有して…というプロセスで得た示唆を地域の財産とするようなことを条件として、リビングラボを公式化していけないかなと思います。さらにいうと、この方法論をそれぞれが身につけていくというのが、リビングラボのいちばんのアウトカムなんだと思います」と中平さんは語りました。
模索するプロセスの共有こそがリビングラボ
3人の提案とフィードバックを終え、ミートアップはフリーディスカッションへと緩やかに移行していきます。知の共有プロセスの具体的な方法論について酒井が投げかけると、先ほどの中平さんのフィードバックを受けた小泉さんもデザイナー的視点の必要性について触れました。
「経営会議などで文字だらけの資料を前に議論がスタックしているようなときに、クリエイターにその資料の世界観を1枚の絵にしてもらうことがあります。そうするとその絵に対する反応が引き出されて議論が促されていく。文字だらけのものよりも共有知化しやすいんですね。これもデザインのセンスが正に必要とされているということだと思います」
それぞれの思考や関係性をニュートラルに越境させるセンスを持った人材、あるいは仕組みにより、具体性を持ったものを真ん中に置くと何かが動き始めるということについては、「静かな水面に最初に石を投げ込むような人間がいないと、そもそも議論が始まらない」と大庭さんもいいます。

また、リビングラボにおいては企業と地域住民では参加する目的が違うという前提のもと、「自律分散協調型の社会をつくっていくにはある程度の協調は必要だけれど、必ずしも連携する必要はない」と中平さん。協調しながら対話をしていくことによって、それぞれが必要な示唆を得るというのがリビングラボのあり方です。それを受けて須崎さんも先日参加したという多摩市の「若者会議」での気づきを共有。誰でも参加できて多様性を尊重しあえる議論が生まれる場には、それ相応の方法論や仕組みがあるようです。
さまざまな視点の共有があったフリーディスカッションの最後に、中平さんはこう語りました。
「今、私たちは誰からも教えてもらっていない“社会の再構築”に取り組んでいますが、それを一緒に模索するということが必要であり、そのプロセス自体もある種のラボなのだと思います。小さな実験や思考を重ねることを民間企業も行政もやっていかなければならないですし、市民もこれからの暮らし方を個々に考えていかないといけない。そしてそれぞれが模索して得たものを共有し知恵を出し合う場としてのリビングラボが、これからは地域にとって価値の大きなものになるのではないかと思っています。その積み重ねが共有知となり新しい社会の方法論みたいなものを形づくっていくのではないでしょうか」

たくさんのキーワードが出て、リビングラボの要素がかなり明確に見えてきた今回のミートアップ。まだまだ議論を深めたいといったムードのなか、タイムアップとなりました。しかし、こうした議論の場こそがひとつのリビングラボであり、この積み重ねによって多摩エリアの「どこでもリビングラボ」が形づくられていくのかもしれません。
※1 「The Green Drinks Code」というルールを守れば、誰でも開催できるイベント。日本では2007年からスタートし、北海道から沖縄までのべ90か所以上で開催されている。
※2 個人が持つ知識や経験(暗黙知)を組織全体で共有し新たな発見を得るためのフレームワーク。「共同化」「表出化」「連結化」「内面化」という4つのプロセスで構成される。